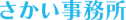著作権登録
著作権とは?
著作権とは、思想や感情を創作的に表現した著作物に対して、自動的に与えられる権利です。
与えられる権利
また、日本も加盟しているベルヌ条約等により、原則として、加盟国の著作物は、日本で保護を受け、日本国民の著作物も加盟国で保護を受けます。
なお、物に固定されたものがあれば、その物自体の権利は、所有権になります。
与えられる権利
- ・著作物の第三者の利用を一定範囲で制限する「財産権」(譲渡、相続可能)
- ・著作者の著作物に対する意思等を守る「人格権」(譲渡、相続不可)
また、日本も加盟しているベルヌ条約等により、原則として、加盟国の著作物は、日本で保護を受け、日本国民の著作物も加盟国で保護を受けます。
なお、物に固定されたものがあれば、その物自体の権利は、所有権になります。
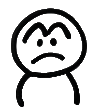 < 左向いて口の開いた犬 を描く
< 左向いて口の開いた犬 を描く『左向いて口の開いた犬』は、アイデアなので著作権の保護の対象にはなりません。
↓
創作

創作的に表現した著作物になりますので、著作権の保護の対象になります。
*額縁に入った絵自体の権利は、所有権になります。
*公表・非公表、上手い・下手、完成・未完成など関係ありません。
*保護も絶対的なものではありません。よって、盗作ではなく、偶然、上記の絵と同じような絵を第三者が描いた場合も、その絵は、その第三者の著作権として保護されます。
著作権の登録制度とは?
日本の著作権制度では、登録は権利の発生要件ではなく、証明や対抗(権利主張)の手段です。
著作権を有することの証明や著作権に基づく権利を主張する必要が生じる可能性がある場合は
著作権を有することの証明や著作権に基づく権利を主張する必要が生じる可能性がある場合は
- ・著作物を公表する。
- ・著作権(財産権としての著作権)を譲り受ける。

公表していなければ、この絵の存在を第三者が知る由がない。
公表しても、必ず盗作されたり、勝手に使用されるものでもないですが・・・
プログラムの著作物の著作権以外は、公表していなければ、登録することはできません。
登録できる内容
*推定とは:反証がない限りその事実を正しいと認めること
著作権の保護期間
著作権法
(保護期間の原則)
第五十一条
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条
変名がその者のものとして周知のもの の具体例は
夏目漱石(変名)→ 夏目 金之助(実名)
無名又は変名で公表していた著作物を上記実名の登録をしておくと、公表後70年から死後70年にかわります。
--
| 登録の種類 | 内容 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 実名の登録(第75条) | 無名又は変名(雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの)で公表された著作物の著作者は、実名を登録できる。 | その登録された人物が「著作者である」と法律上推定されます。 |
| 第一発行年月日等の登録(第76条) | 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 | 登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。 |
| 創作年月日の登録(第76条の2) | プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。 | 登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。 |
| 著作権の移転等の登録(第77条) | 移転若しくは信託による変更又は処分の制限、質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限を登録できる。 | 権利の変動を第三者に対抗すること(権利主張)ができます。 |
| 出版権の登録(第88条) | 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限、質権の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限を登録できる。 | 権利の変動を第三者に対抗すること(権利主張)ができます。 |
著作権の保護期間
著作権法
(保護期間の原則)
第五十一条
- 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
- 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条
- 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 --
- 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
- 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
- 二 前項の期間内(その著作物の公表後七十年を経過するまでの間)に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
- 三 著作者が前項の期間内(その著作物の公表後七十年を経過するまでの間)にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
無名又は変名で公表等している場合は、原則、誰が著作者か特定できません。
よって、公表から70年となっています。
ただし、無名又は変名であっても、誰が著作者か特定できる場合(以下第2項)は、原則通りその人の死後70年保護されます。
--
変名がその者のものとして周知のもの の具体例は
夏目漱石(変名)→ 夏目 金之助(実名)
無名又は変名で公表していた著作物を上記実名の登録をしておくと、公表後70年から死後70年にかわります。
--
NFTと著作権
NFT(Non-Fungible Token/非代替性トークン)とは、ブロックチェーン技術を利用して作られた「唯一無二のデジタル証明書」のことです。
簡単にいうと、 「このデジタルデータは世界に1つだけ!本物はこれ!」 と証明するための技術です。
つまり、NFTを購入すると、そのデジタルデータにひもづく「トークンの所有権」は、あなたのものになります。
しかし、著作権は、原則として著作権者に残ります。
簡単にいうと、 「このデジタルデータは世界に1つだけ!本物はこれ!」 と証明するための技術です。
つまり、NFTを購入すると、そのデジタルデータにひもづく「トークンの所有権」は、あなたのものになります。
しかし、著作権は、原則として著作権者に残ります。
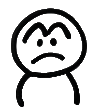 < 左向いて口の開いた犬の画像、売ってあげる
< 左向いて口の開いた犬の画像、売ってあげるデジタルなので、無限に複製が可能

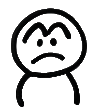 < NFT化したよ
< NFT化したよ <買います。
<買います。
↑画像を勝手にグッズ化したりできません。
登録にかかる費用
著作権の登録先は、文化庁になりますので、文化庁に以下の登録免許税を納める必要があります。
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄) 別表第1
著作権の登録等
コンピュータ・プログラムは、プログラム著作物として、指定登録機関の 一般財団法人ソフトウェア情報センターに登録をします。
登録免許税とは別に手数料1件 47,100円がかかります。
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄) 別表第1
著作権の登録等
| 登録の種類 | 課税標準 | 登録免許税(1件) |
|---|---|---|
| 移転の登録 イ 相続又は法人の合併 ロ その他の原因 |
著作権の件数 著作権の件数 |
1件につき 3,000 円 1件につき 18,000 円 |
| 実名登録 | 著作物の数 | 1個につき 9,000 円 |
| 若しくは第一公表年月日又は創 作年月日の登録 | 著作権の件数又 は著作物の数 | 1件又は1個につき 3,000 円 |
| 出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 1件につき 30,000 円 |
登録免許税とは別に手数料1件 47,100円がかかります。
当事務所にご依頼の場合は
上記の登録免許税、手数料以外に以下の報酬がかかります。